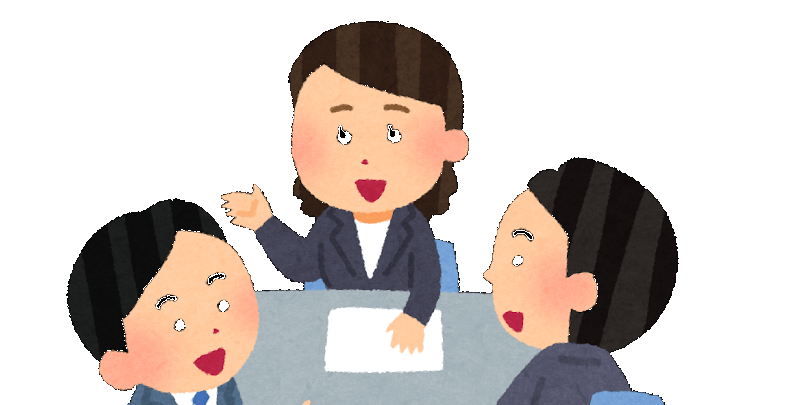エホバの証人だった子ども時代、何が一番つらかったのかとよく考えてみたら、自分の良心に反するエホバの活動をしなければいけなかったこと、そしてエホバの証人の子どもたちが虐待を受けるのを見ていても、何も行動を起こすことができなかったことかなと思います。
自分たちだけが正しくて、信者以外の人たちは悪魔サタンに支配されている、間もなくエホバの証人以外の人たちはハルマゲドンでエホバに滅ぼされるという教義を広めて、新たな信者を獲得するよう伝道(布教活動)しなければいけなかったことは、今でも自分を苦しめています。
エホバの証人2世の方々や、信者たちから忌避をされている方々が、今も非常に苦しんでいる状況を知るにつれ、「なぜ、エホバの証人として集会に出席していた頃、壇上で講演をしていた信者のマイクを奪い取って、『子どもたちを虐待するのはやめてください。子どもたちに信教の自由、進学・就職の自由を与えてください。忌避はやめてください』と言わなかったのか」と過去の自分のあまりの勇気のなさに嫌気が差すようになりました。
当時の自分にできたことは、自分の良心を押し殺してただ耐えること、冷酷で残酷で、矛盾する教えを説く「愛の神、エホバ」の教義を考えないようにし、死なないように生きていくことでした。
先日、ネットで「愛の神 エホバ」で検索してみたところ、教団の公式ホームページの「エホバ ― 残酷な神か,それとも愛に富む神か」(エホバの王国を告げ知らせるものみの塔 1985)というタイトルの記事などが出てきてました。近年でも、「エホバは愛の神」と強調する記事が多く出ており、いかにエホバが愛に富んでいる神なのかを力説し、納得させようとする文章でしたので、信者たちの中に「実際には全然愛の神ではないよね?」と気が付いていらっしゃる方も増えてきたので、このような記事を公開するのかなと思いました。

子どもの頃から限界を感じた時に自分に言い聞かせていた言葉のうちの一つは「あと一日だけ生きてみよう」という言葉でした。
かなり昔に、『だから、あなたも生きぬいて』(大平光代 著)という本に出会った時に、「ご著者の大平さんは、壮絶な経験をされながら、ものすごい努力によって弁護士になられたんだ!だったら大平さんほどひどい目に遭ったわけではない私なら、なおさら生きていけるはずだ」と感じ、勇気をもらっていました。
なお、大平さんの経歴については以下の通りです。
中学2年生のとき、いじめを苦にして割腹自殺をはかる。その後、自暴自棄になり非行に走る。16歳で暴力団組長の妻になり、背中に刺青をいれるほどに。6年間極道の世界に生きた後、養父・大平浩三郎氏と出会って立ち直る決意をし、猛勉強を開始。「宅建」「司法書士」と次々と合格し、29歳で最難関の「司法試験」に一発で合格する。現在、非行少年の更生に努める弁護士として活躍している。
(『だから、あなたも生きぬいて』表紙裏より引用)
大平さんはそれまでの交友関係から抜け出し、養父の大平さんやご友人たちの応援を受けて猛勉強に励むのですが、特に本の最後のところにあった下記の解説の文章が心に響いていました。
「自分の存在価値を認めてほしい、自分を理解してほしい」ーそんな大平さんの思いを、彼らが受け止めた。大平さんは、「この人たちの中で生きていきたい」と思うようになった、と語っている。
生きていれば、そういう出会いもきっとある。今を苦しんでいる子供に、5年、10年先のことを想えというのは、酷だろう。でも、せめて一日、あるいは半日、せめて5分でいいから、とりあえず生きてみて、それから考えようと、声をかけることはできないだろうか。「判断の先延ばしは、悪いことばかりではないよ。5分経ったら、次の5分、そしてさらに5分…その中で、必ず何らかのチャンスに巡り合える。『だから』あなたも生きぬいて」と。
「そうだよね、『あと一日だけ生きてみよう』っていう考え方は、間違ってないよね。現に、その言葉に支えられながら、私はこうして大人になっても生きているんだし、私のことを理解してくれる友人にも恵まれたわけだし…」と今年、久しぶりにこの本を読み返しながら思いました。
今年は特に落ち込むことが多かったのですが、精神状態が逆もどりしてしまった場合には、過去に読んで良かった本を読み返すのも有効だなぁと感じています。
未だに当時の自分を責めてしまい、非常に落ち込んでしまうこともありますが、自分の本当の気持ちを言うことを許されず、何も行動を起こせなかった子ども時代を悔やむよりも、今の自分にできることをこれからもやっていきたいと思います。