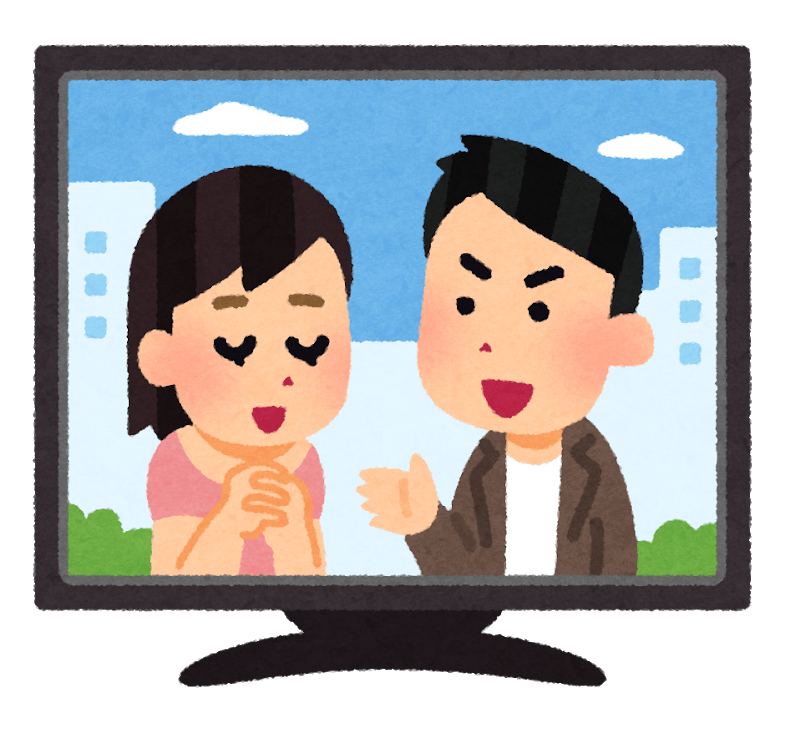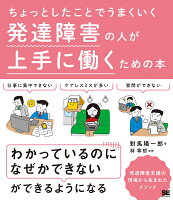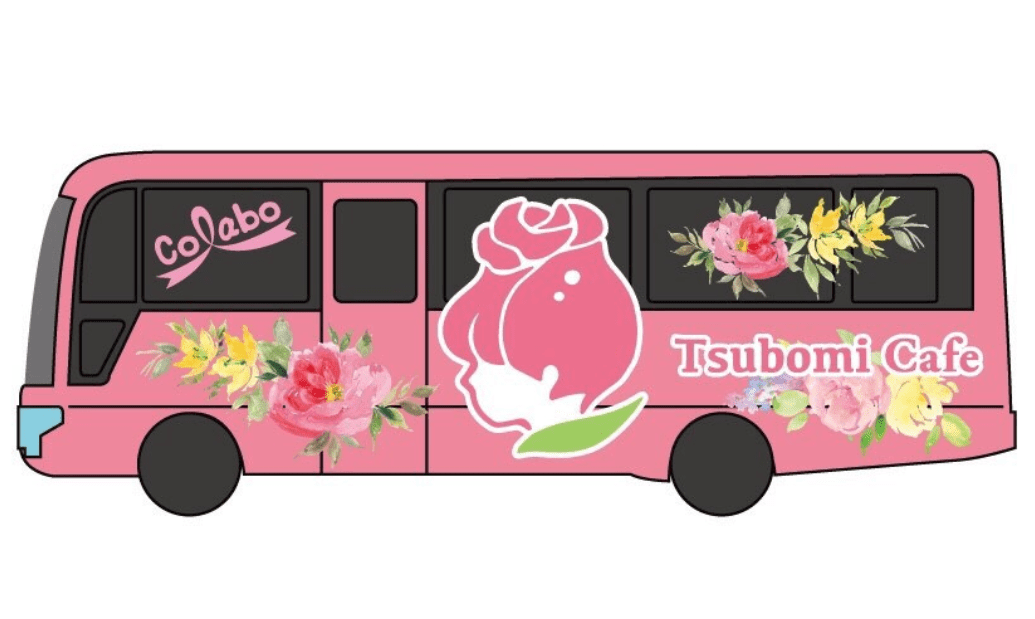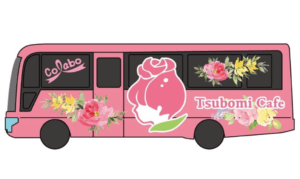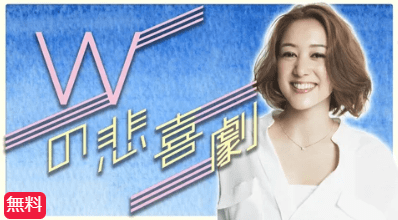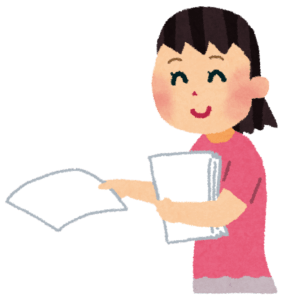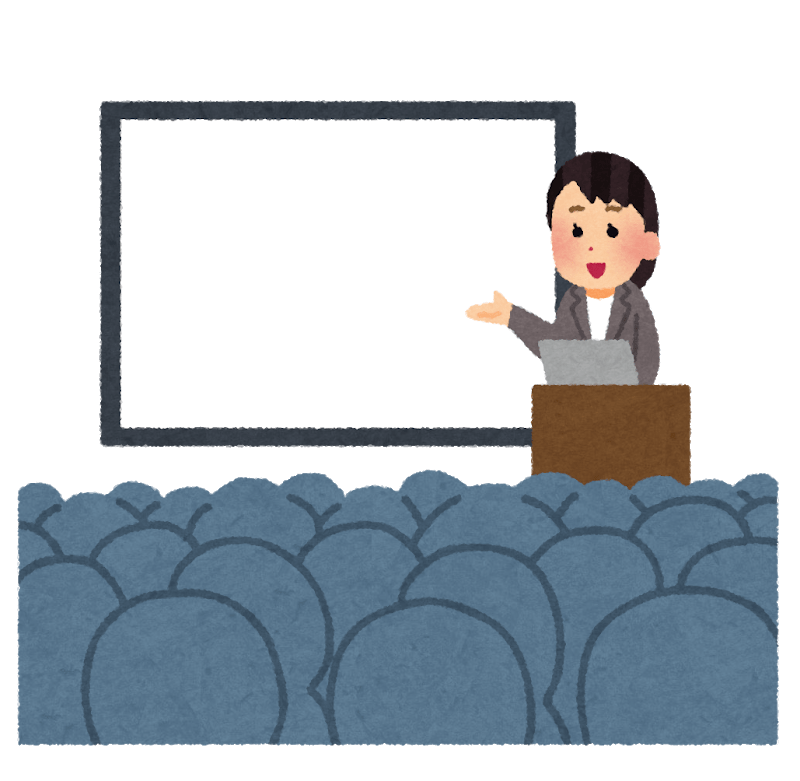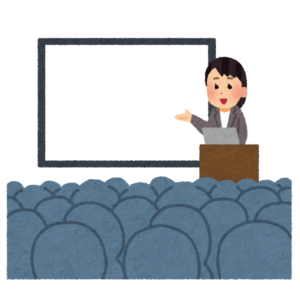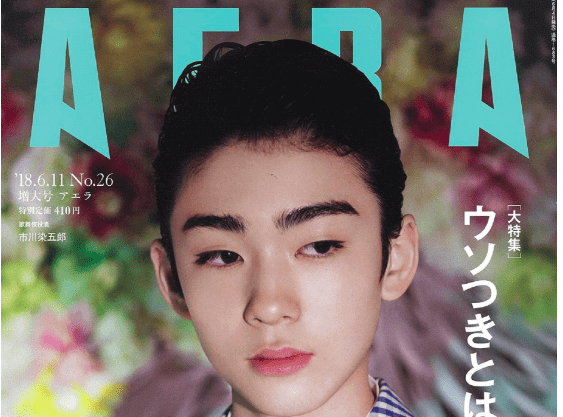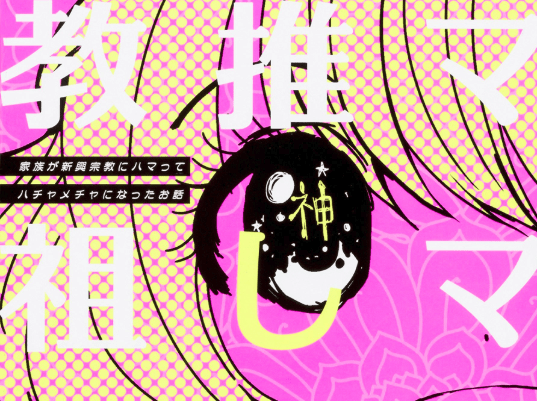以前の記事に対するSAKURAさんのコメントへの返信で、これからは「発達障害」という言葉はできるだけ考えないようにしていく、と書き、今もその思いは変わらないのですが、私と同じような症状を持つ方や、そういった方に関わる方の参考になるかと思い、これまで私が経験してきたこと、自分なりの対策を羅列してみました。数か月前から書き始めていたこの記事を最後に、今後は発達障害についてはできるだけ考えないようにしていきたいと思います。
とはいえ「発達障害」と一言で言っても、症状や程度は千差万別です。相貌失認や虐待のトラウマを併せ持つ私の場合の例として参考程度に読んでもらえたらと思います。
大変なこと、嫌な思いをしたこと
感情がなく冷たい人と思われることがあります
ボーっとしていることが多く、以前、「クスリでもやってんの?」と、小学校時代の元クラスメイトに言われました。念のため書いておきますが、私は病院でモルヒネを投与されたことがある以外、薬物を摂取していません。
さらに、考え事をしていると返事をすることができないことも多く、また勘違いや思い込みも激しいため意図せず傷付けるようなことをしてしまうのと、忘れっぽいこともあり、冷たい人間だと思われることがあります。「ミュージカルとかを観て、心を豊かにしたほうが良いよ」と言われこともあります。
自分としては精いっぱい頑張っているつもりなのですが、感覚がずれているらしく、善意が裏目に出てしまうことがあります。
変なところで気を遣ってしまいます
昨年、心療内科の受診のためにクリニックに行った際、エレベーターの中で女性に「すみません、私、今日予約はしていないんですけど…。初めて受診するんですけど、このクリニックって、結構お金がかかりますか?」と聞かれ、私は心の中で「あー、このクリニックは予約制なんだけどなあ…。でもがんばってここまで来られたんだから、ぜひ受診していってほしいなあ。金額は私も分からないしなあ…」と思いました。
できるだけ明るく「私も初めてなので詳しくは分からないですが、すごく高額ということはないと思いますよ。念のため受付で聞いてみてはいかがでしょうか?」というようなことを答えた気がしますが、別れた後で「さっきの方、無事に受診されたかなあ。もしかしたら私の対応のせいでやっぱり引き返した、ってことはないかなあ。」と心配していました。
人の心配をする前に、自分の受診に集中しろ、と突っ込みたくなりますが。
不安に思っていることが色々あります
ある相貌失認の症状を持つ方は、心ない人に「私が誰だか分かる?」と試されるようなことをされて傷つくことがあると聞いて、私もそういうことをされるのかなと不安になりました。
文章を書くのは子どもの頃から好きなので、ある程度文章を書くことはできるのと、いつもできるだけ明るく振舞っているため、「悩んでいるようにはとても見えない」とつい最近も言われたので、このホームページで書いている内容と実際の自分とのギャップがあると思われるかもしれないと思っています。
「チラシ配りをしている人がいたら、受け取ろう!」と思っていても考え事をしていたり急いでいたら受け取らないし、知り合いに会っても気付かないことも多くて挨拶ができないので礼儀を知らない人のように映っているかもしれないなぁと思っています。
そして、忘れっぽいです。コメントやメールに返信をしたつもりになっていて、していなかったことに数年後に気が付いたりします。
また、緊張し始めると言い間違えがすごいです。例えばラーメン店のアルバイトでしょうゆラーメンとご飯を提供しようとした際、「しょうゆご飯です」と言いながら出してしまいました…。すぐに気が付いて言い直したため、お客さんは「大丈夫ですよ~」と笑ってくれましたが…(^^; 友人からも後から指摘されることがあるため、多分、自分の気が付かないところで相当言い間違えをしているんだろうなと思います。
思い込みが激しく、様々なことを理解するのに時間を要することがあります
思い込みが激しく、自分にとって都合の良い情報しか入って来ない時があります。しかも友人がそれを指摘をしても聞き流していたり、言われたことの意味を勘違いしていたりして、そのことに気が付くまで数か月~数年かかることもあります。
たとえば以前、新しい仕事をしようとしていた時、友人のうち一人だけ「あなたにはこの仕事は向いていないからやめたほうがいい」と忠告してくれていましたが、どうやらそれを聞き流していたようで、他の友人たちは応援してくれていたこともあり、開業してしまいました。
その後、その仕事がうまくいかずに辞めた時に、「ほら、だからあれほど言ったのに…」とその友人に言われた時、どんなに思い出そうとしても忠告は全く記憶になかったので、自分の脳が信じられなくなりました。最近は、「今、ちゃんと聞いてた?要点を言って」と確認されます…。
学力と症状は無関係だと思います
ボーっとしている時もあれば、しっかりしている時もあり、また学校の勉強は問題なかったため、ありえない言動が起き始めると「わざとやってるの?」と言われてしまうこともあり、誤解されるのが辛いです。
義務感、正義感が強過ぎ、思考回路が独特、脳が暴走することがあります
もともと「困っている人がいたら助けなきゃ」と思う傾向がありましたが、2013年の大病を機に人類に対する愛が止まらなくなりました。高熱で脳がやられたのかもしれません。
「自分が死ぬ前に、できる限りのことはやらないと。可哀そうな人がいたら助けないと」という変な義務感、自分勝手な正義感が暴走し、あり得ない行動に出たりすることもあります。友人から「危険過ぎる。その理論が理解できない。思考回路が独特過ぎる。良い動機でやっていても、相手にとっては迷惑でしかない。」と言われたことがあります。
最近は友人たちの忠告を聞いて、よくよく考えて行動するように心がけてはいますが、ほぼ無意識のうちに電車内で見知らぬ泣いている赤ちゃんをあやしたりしていることがあります。
知り合いが多く集まる場所は苦手です
遊園地のような不特定多数が集まる場所は平気なのですが、同窓会や何かの講座などの2回目以降(ある程度顔見知りができ始めた頃)に参加するのが苦手です。
人は好きなのですが、知り合いが多く集まると「人違いをしないように気を付けなければ」と思って大変なエネルギーを使い、疲れます。小学校の同窓会には一度だけ参加したことがあり、元クラスメイト達と再会できたのは嬉しかったのですが、すぐに「これは私の脳が処理できる限界を超えている…」と感じたのでお酒に逃げることにし、結局飲み過ぎて後半はずっと寝ていました…。
過集中の傾向があります
昨年、自分が発達障害の要素を持っていると知った時、「まずい!自分の障害のせいで、子どもたちの命を危険にさらすかも」と不安になり、これまで勉強してきた、保育時の事故や病気の時の対応内容をノートにまとめ直しました。念には念を入れて、最後に「救急は119番」まで書き入れました。
連日、ほとんど休憩を取らずにまとめる作業をしていたら、首が寝違えた時のようにあまり回せなくなってしまい、その症状が数日続いたので、病院に行きました。レントゲンを撮ったところ、骨に異常はないとのことで、恐らくずっと同じ姿勢で作業をしていたことによって筋肉が固まってしまった(?たしかそう言ってた気がします)ようです。まあ、治ったので良かったですが…。
会話に集中することが難しいことがあります
人と会話をしている最中、意識がどこかに飛んでいても、普通に返事をしていて会話が成立していることもあるらしいため、後日全く会話の内容を覚えていなくて相手にびっくりされることがあります。
いつも一生懸命話を聞こうとしていますが、私がとんちんかんな返事をしたため「バカにしてるのか!!」と相手が激怒したこともあります。
後先を考えず仕事を辞めようとしてしまいました
発達障害の本に、保育の仕事は向いていない、といった内容が書いてあったこともあり、緊急時の対応をまとめる作業をしながらも「保育の仕事は辞める」と言い出しました。
社会経験の長い友人が「早まるな!今まで努力でカバーしてきたんだから、大丈夫。何よりも子どもたちに好かれているんだし。川島さんの性格から考えても、現時点で一番合っているのは保育の仕事なんだから。第一、仕事を辞めてどうやって食べていくの」と引き留められ、たしかにそうだと思い、続行することにしました。
ただ、過去にささいなことでパニックになり救急車を呼んでしまい、救急隊員に平謝りをしたことがあったので(子どもは無事だったので何よりですが、救急隊員の方に余計な出動をさせてしまいました…)、今でも「保育の仕事は好きだけど、自分の障害のせいで事故を起こしたら取り返しがつかない…」と早く新しい仕事をしたい衝動にかられます。
でも、新しい夢の実現には、まだまだ時間がかかりそうなので、とりあえず今は「やれるだけの事前の準備や対策はやってあるんだから大丈夫」と言い聞かせながら保育の仕事を続けています。
嬉しかった言葉
昨年から今年にかけては自分の顔を鏡で見ても、誰なのか分からないことが数回あったため、「ついにここまで来たか…」と嫌になりました。子どもの頃、自分の家族の顔も分からなかったことがあり、「すみません、どちら様でしょうか?」と言ったこともあるため、もしかしたら将来の夫にも、同じことを言ってしまうかもしれないという不安があります。
そんな悩みをアルバイト先の先輩に漏らしたところ、「大丈夫だよ。きっと旦那さんは、自分のことを忘れないでいてもらうために、真彩さんのもとにいち早く帰ってきて、大事にしてくれるよ。色んなことを忘れてしまうみたいだけど、その分、いつまでも新鮮な気持ちで付き合えるよ」と言ってくれました。
「あれ?ちょっとおおげさに伝わってしまったかな?」と心の中で思いながらも、初対面の私に、言葉を選びながら慰めてくれた優しさが嬉しかったです。その方も入院を繰り返している方だったので、人の辛さを理解してくれる方なんだなと思いました。
また、友人たちから「行動力がすごい」「あなたにはどんなことも乗り越えられる力がある」と言ってもらえたこと。割と単純なので、「そっかあ!」と嬉しくなります(*^^*)
世の中を生きていくための対策
こんな私が、世の中を生きていくためには準備や対策が必須です。今までの人生での失敗から自分なりに編み出した対策を紹介します。
座席表を作成していました
子どもの頃からクラスメイトを覚えるのが苦手だと感じていたので、新クラスになると自由帳に席順と名前を書いて、何度もその紙とクラスメイトの顔を照らし合わせて覚える作業をしていました。
あらかじめ症状を伝えています
親しい人には、自分が相貌失認の気があることを伝えてあります。そのため、私が相手に気が付かなくても「悪気はないんだな」と理解してもらっています。
待ち合わせで人違いを防ぐために
「この人かな?」と自信がない時には、すぐ近くで電話をかけてみて、その人が電話に出るかどうかで合っているかを判断しています。
部屋に子どもたちの写真を貼っています
自分の部屋に、保育している子どもたちの写真を貼っています。以前、何年も保育していたある女の子に、休日に街で声を掛けられた時、私はその子が誰なのか分からずしばらく固まってしまったことがあります。その子が悲しそうな顔をしたので、やってしまったと思いました。そんなこともあり、たとえ自分の顔は分からなくなっても、子どもたちの顔だけは絶対に忘れないように、毎日写真を眺めるようにしています。
スケジュール帳を失くしたらすべてが終わるので、絶対に失くさないようにしています
スケジュールを覚えられないので、なんでもスケジュール帳に書き込むようにしています。毎日寝る前に、翌日の詳しいスケジュールと持ち物、電車の時間や、そこから逆算した家を出る時間を紙に書いています。ただし、少し早めの時間から翌日分のスケジュールを書き始めることもあり、夜にそれをすっかり忘れていて、紙2枚に同じことを書いてしまうこともありますが…(^^;
スケジュール帳を失くしたら、全てが終わるので、絶対に失くさないようにしています。以前、大雨の日に携帯電話を濡らしてしまい、全データが消えた時は死ぬかと思いましたが、それと同じレベルのダメージです。
万一に備えて、何かの本で紹介されていた、「これは大切な手帳です。もし拾った方は下記までご連絡下さい。5,000円差し上げます。[携帯番号]」という文章を書いてあります。なお、5,000円というのがちょうど良い金額なのだそうです。少な過ぎると、拾った人はわざわざ連絡しようとは思わないし、多すぎると、何か怪しいと思って逆に連絡してくれないそうです。
さらに、自分の住所や電話番号も思い出せなくなることがあるので、毎年手帳に書いています。
仕事のために念入りに準備をしています
仕事の時もアルバイトの時も、その日覚えておくべき内容を小さめの紙に書いて、携帯しています。そのため、仕事の準備に時間を取られますが、自分の場合はこのような作業をしないと仕事になりません。高校生で初めてアルバイトをした時から、記憶の限りずっとやっています。
まあ、どんなに準備をしていてもケアレスミスも多いので、保育している子どもに「ごめん!悪気はないんだよ!ほんとごめんね!」と謝って、「考えすぎだよ~。大丈夫だよ~!」と言ってもらったりしていますが…(^^; また、新しく覚えることがある時には単語カードを活用しています。
時間をかけて記事を書いています
記憶が混乱しやすいため、資料や記録を参考にしたりじっくりと思い出しながら記事を書いています。内容や脳の状態によっては1つの記事を書くのに100時間以上かかることもあります。
記憶が間違っている可能性もあるので記事に書いていることが100%事実だとは断言はできませんが、もし間違いに気が付いたら修正しようと思いながら、その時その時のありのままの状態で書いています。ハイになっている時は痛い感じだし、落ちている時は自分でも危ないなあと思うくらいです。
今も果たして自分の発達障害について公表したことを後悔していないかと問われたら答えることはできません。
生きづらさを抱えながら生きている方々が、より暮らしやすくなる社会になることを願っています。